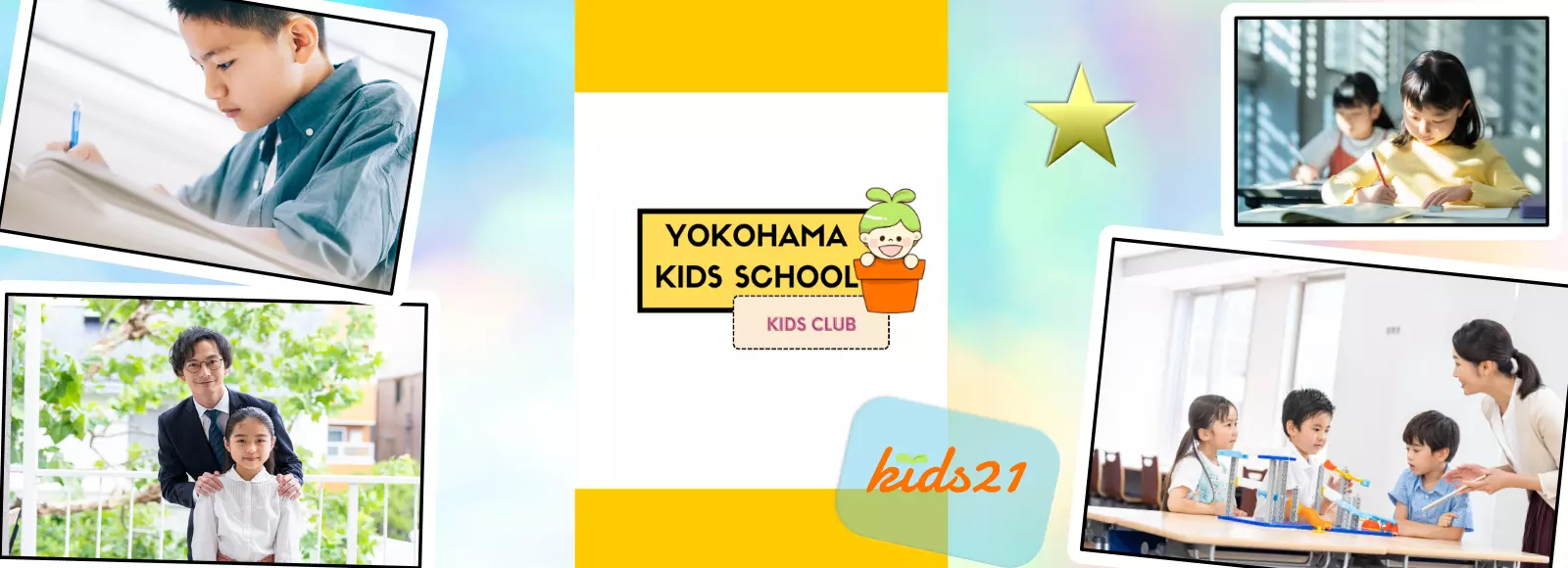幼児の成長に適した環境とは?モンテッソーリ教育の敏感期から考えてみる

子どもの成長に良い環境とは、どのようなものなのでしょうか。
我が子には少しでも良い環境で育ってほしいと思うものですが、その環境づくりに迷う方は多いかと思います。
そこで今回は、モンテッソーリ教育の敏感期という考え方をもとに、子どもの成長を促す環境づくりについて詳しく説明していきます。
Contents
モンテッソーリ教育とは

モンテッソーリ教育は、イタリアの医師マリア・モンテッソーリが子どもを観察することによって生み出した教育法です。
1907年に最初のモンテッソーリ教育を行った「子どもの家」の設立から、世界中に広がり、現在では110か国以上でモンテッソーリ教育が実践されています。
モンテッソーリ教育を受けた有名人として、将棋の藤井聡太棋士、マイクロソフト創始者のビル・ゲイツが挙げられます。
モンテッソーリ教育の考え方
モンテッソーリ教育は、子どもには自分で自分を教育する力である自己教育力が備わっているという考え方に基づいています。
そして、自己教育力が発揮されるためには、この子どもの発達段階に見合った環境が必要だと考えられています。
子どもは、自分の置かれた環境に順応し、環境から学ぼうとしていきます。
言葉を教えなくても話そうとする、誰も教えなくても歩こうとするなど、子どもは大人が教えなくても、見聞きするだけでたくさんのことを覚えていきます。
モンテッソーリ教育では、子どもの発達を援助するために子どもの発達に見合った環境を用意していきます。
大人が子どもに何かを教えることはありません。
子どもには環境から自ら学ぶ力があり、適切な環境の中に身を置けば、自発的に成長していくと考えられているからです。
モンテッソーリ教育の特徴
モンテッソーリ教育には、「教える」ことが存在しません。
そのため、子どもが主体的に活動できるような特徴をもっています。
ここからは、モンテッソーリ教育の特徴について説明します。
・子ども主体である
モンテッソーリ教育は、子ども主体の教育法です。
大人が言葉で教えず、子どもに活動の方法をゆっくり見せることで、子どもが正しい活動方法を知るのです。
大人の見本を見た子どもは、試行錯誤しながら大人の動きに近づくために活動していきます。
例えば、モンテッソーリ教育には蝶々結びをする活動がありますが、大人は最初にゆっくりとやり方を見せるのみです。
子どもはその見本を見て、自分で蝶々結びができるように練習していきます。
その過程で、手先の使い方を覚えていくのです。
子どもは自分の望む活動を繰り返し、さまざまな能力を身につけて成長していきます。
大人が教えるのではなく子どもが主体となって活動を行う、これがモンテッソーリ教育の大きな特徴のひとつです。
・子どもを観察する
モンテッソーリ教育は、子どもを観察することで生み出された教育法です。
観察することで子どもが求めていることを理解し、それに応じた環境を作っていきます。
子どもが「何をしたか」だけでなく、どのように選んだか、どのように集中していたか、体の動きはどうだったかなど、細かい部分まで見て、子どもの発達状態を理解していきます。
そして、その分析をもとに子どもに見合った環境を用意していくのです。
・環境を整える
大人は、観察して分かった子どもの発達段階や興味・関心に見合った環境を作っていきます。これを「環境を整える」と言います。
環境には、人的環境と物的環境の2種類があります。
子どもが興味を持つものが揃えられていても、正しい使い方をしなければ意味がありません。
例えば、はさみの使い方一つでも、紙に沿える手の位置やはさみの持ち方が間違っていたら、ケガをしてしまうかもしれません。
子どもが正しい方法を知ることは、安全性の確保にもつながっていきます。
最初に大人が使い方を分かりやすく見せることで、子どもは活動に取り組むことができます。
大人(人的環境)が、子どもと活動(物的環境)を結びつけることで、子どもは活動し、成長していくことができるのです。
・「おしごと」をする
モンテッソーリ教育では、「おしごと」と呼ばれる活動をすることで子どもの発達を促します。
おしごとは、日常生活の練習、感覚教育、言語、数、文化の5つの分野に分かれています。
例えば、日常生活の練習では、歩く、椅子に座る、洋服の着脱など、普段の生活で行う動作を練習していく過程で、自分の身体の動かし方を学んでいきます。
感覚教育は、複数ある色のついた板をグラデーション順に並べる、目隠しをして布を触り同じ種類のものを当てるなど、五感を刺激するような活動をとおして、自分の感覚器官を育て、観察力や思考力を養うことを目的としています。
このように、分野によって活動内容や目的は異なります。
それぞれの分野のおしごとをするなかで、子どもはたくさんの能力を身につけ、成長していくのです。
・教具をつかう
教具とは、モンテッソーリ教育で使う教材のようなもので、おしごとをするときに使います。
子どもが自発的に、正しく教具を使って活動することで、子どもの知能が発達していきます。
教具は、子どもの発達に応じたレベル、つまり、その子の現段階のレベルより少し上のものを使うことで、新たな能力を獲得することができます。
モンテッソーリ教育では、子どもは自分の周辺環境から多くのことを吸収し成長していくと考えられています。
大人の役割は、子どもの発達段階に見合った環境を整えることです。
整えられた環境の中で主体的に活動して得た学びが、子どもを成長させていくのです
敏感期とは

敏感期とは、自分の能力を伸ばそうとして、ある特定のことに夢中になる時期のことです。
もともとはオランダの生物学者デ・フリースが使った生物用語ですが、モンテッソーリは敏感期が人間の子どもにも存在すると考えました。
敏感期は、幼児期に一時的に見られ、その期間を過ぎるとなくなってしまいます。
この時期の子どもは、自分の発達に必要な行動を夢中で何度も行うといわれています。
子どもが特定の物事にこだわったり、同じ行動を何度も繰り返したりするのも、敏感期の影響かもしれません。
敏感期の種類
敏感期は、その興味の対象によっていくつかに分かれています。
ここでは、子どもに現れる敏感期を種類別に紹介していきます。
・言葉の敏感期

4ヶ月~3歳ごろに見られます。
言語に強い興味を持ち、言葉を話せない時期でも周囲の話を聞くことで、言葉の音、強さ、長さなどを学習します。
見たものの名前を聞いたり、口に出したりする、大人の言葉を真似するなどの行動が見られます。
・秩序の敏感期

0歳~3歳ごろに見られ、2~3歳にピークを迎えます。
まわりの環境にあるものを「秩序」として自分の中に記憶していく時期で、順番、場所、習慣などに強いこだわりを持ちます。
毎日の行動や物の置き場などがいつもと同じだと心の安定を得られます。
逆に、いつもと違うことがあると子どもの中の秩序が乱れて不機嫌になってしまうことがあります。
日常の中にある秩序が安定することで、子どもは自分の中に秩序を作り上げていきます。
この内的秩序が、順序立てて考える力や整理された思考を形成するのに役立ち、論理的思考力につながっていくのです。
・運動の敏感期

2歳半~4歳半ごろに見られます。
歩く、座る、持つなど、生きていくために必要な動作や動きを獲得しようとする時期です。
周りの大人の行動を観察し、同じように真似しようとします。
自分でできることは自分でやりたがる時期です。
・小さいものへの敏感期

1歳3か月~3歳ごろに見られます。
小さな生き物や物に夢中になり、触ったり集めたりする時期です。
散歩中に小さな虫を見つめている、床のゴミを拾ってくるなどの行動が見られます。
小さいものを見ることで観察力が身につき、触ることで指先をうまく動かせるようになります。
・感覚の敏感期

2歳~6歳ごろに見られますが、ピークは3歳~3歳半です。
五感が洗練されていく時期で、五感を刺激するものに強く反応します。
生まれてから3歳ごろまでは、五感を刺激することで感覚器官を発達させていきます。
その後は感覚的な印象を頭の中で整理し、自分の周囲にあるものを分類していきます。
・作法と社会性の敏感期

2歳~4歳ごろに見られます。
自分の行動を意識し、大人を真似しようとする時期です。
社会の中で過ごすうえで必要な、生活習慣や礼儀を吸収していきます。
社会性や道徳観、倫理観も身につけ始め、集団行動への愛着が芽生え始めます。
敏感期とは、子どもがある能力を獲得するために一時的にみられる特殊な感受性のことです。
言葉、秩序、運動、小さいもの、感覚、作法と社会性の6種類に分けられます。
敏感期の子どもは、その敏感期に関連する物事に夢中になり、何度も繰り返す過程で成長していくのです。
・子どもに適した環境のポイント

モンテッソーリ教育の敏感期は興味の対象によって分けられ、その出現する時期も異なってきます。
子どもの敏感期に適した環境を整えることで、効率的に能力を身につけることができるでしょう。
そこでここからは、子どもに適した環境を整えるためのポイントを見ていきましょう。
子どもが自分でできるような環境づくり
敏感期の子どもは、能力を獲得するために、特定の活動に夢中になります。
その衝動は一日のなかでいつ現れるかわかりません。
そのため、子どもが活動したいと思ったとき、すぐにできるような環境を整えておく必要があります。
例えば、低い棚やおもちゃ箱を用意する、いつでも使えるように道具のメンテナンスを欠かさない、などのことを心がけます。
子どもが使うものは、一人ですぐに使えるようにしておくことが大切です。
また、道具を用意しても使い方が分からない状態では、子どもの能力を十分に引き出せないかもしれません。
使い方を事前に見せておくことで、子どもが一人で活動することができます。
自由がある
モンテッソーリ教育では子どもの自主性を大切にしています。
つまり、子どもの活動のなかに自由があるということです。
自分が何をするか、どこでするか、いつするかなど、子どもが自由に選べる環境が大切です。
ただし、他の人の集中が途切れる行動やケガをしそうな行動については、ある程度の制限が必要です。
敏感期に合わせる
子どもの周辺環境を敏感期に合わせると、子どもが効率よく能力を獲得していく助けになります。
敏感期は一生に一度しか来ない特別な時期なので、危険がない限りは子どもの行動を制限しないようにしましょう。
危険なものや使ってはいけないもので遊んでいた場合、同じような行動ができる代替品を与えることで子どもも満足できるでしょう。
ここから、敏感期ごとにどのような環境を作ればよいか具体的に説明していきます。
・言葉の敏感期
言語の敏感期の子どもには、多くの母国語に触れる体験が大切です。
言葉を話せない時期でも、たくさん話しかけることで、母国語を吸収していきます。
話せるようになったらたくさんおしゃべりをして、読み書きの段階では文字に触れさせる体験ができる環境を作りましょう。
また、この時期の子どもは大人の話す言葉を真似するので、汚い言葉遣いや使ってほしくない言葉は口に出さないように気をつけましょう。
・秩序の敏感期
「いつもと同じ」であることで心が安定する時期なので、物の置き場、日常のルーティーンなどを統一することが大切です。
もし変えなくてはならない場合は、事前にしっかり伝えるようにしましょう。
子どもの不機嫌を単なるわがままや反抗期で片づけず、しっかり説明することで、子どもが安心することができます。
・運動の敏感期
運動の敏感期の子どもには、たくさん体を動かせる環境を用意することが大切です。
運動には手先を使うことも含まれますので、手を使うおもちゃなどを用意してあげるとよいでしょう。
・小さいものへの敏感期
この時期の子どもが小さいものを手に持ったら、なるべく叱らずに見守るようにしましょう。
見るだけでも観察力は身につきますが、実際に触れることでより多くの情報を得られるからです。
時間を決めずに外に出て、子どもが立ち止まっても急かさず、満足するまで観察させてあげましょう。
子どもが持ってきたものを入れる容器を用意してあげるのも良いかもしれません。
・感覚の敏感期
五感をとおして世界を理解していく感覚の敏感期の子どもには、実際に見たり、聞いたり、触ったりと、五感を使った体験をできる環境が適しています。
身の回りにカラフルなものを置く、音の出るおもちゃを用意する、外に出て自然に触れるなど、五感を刺激することを意識しましょう。
小さい子どもは色々なものに触れようとしますが、危険がない限りは子どもの行動を見守ってあげることが大切です。
・作法と社会性の敏感期
この時期の子どもは、周囲の大人の行動を真似しながら基本的な生活習慣を身につけていきます。
言葉の敏感期同様、大人は子どもが真似しても問題ない行動を心がけましょう。
「おはよう」「いただきます」「ありがとう」など、挨拶をしっかりすること、食事のマナーなど、大人が行動で示していくことが重要です。
また、社会でのルールを学んでいく時期でもあるので、公共の場でのルールを行動で示すと子どもが理解しやすいでしょう。
子どもの周辺環境は、子どもができることは一人で行えるようにしておく、活動をするかどうかは子どもの選択に任せるなど、子どもが主体となって行動できることが大切です。
そのうえで、子どもの敏感期に配慮したものを多く置いておくと、効率的に子どもの成長を促すことができるでしょう。
まとめ
モンテッソーリ教育では、一人一人の子どもの発達段階を見極め、その子に合った環境を大人が整えていきます。
自分の子どもがどの敏感期にあたるのかを見極め、子どものまわりに敏感期に関する体験をたくさんできる環境を用意してあげましょう。
活動中、子どもが上手くできないとつい口を出したくなってしまうかもしれませんが、グッとこらえて子どもを見守ってあげてください。
子どもが伸び伸びと活動し、満足するまで繰り返すことが、子どもの成長にとって最も大切なのです。