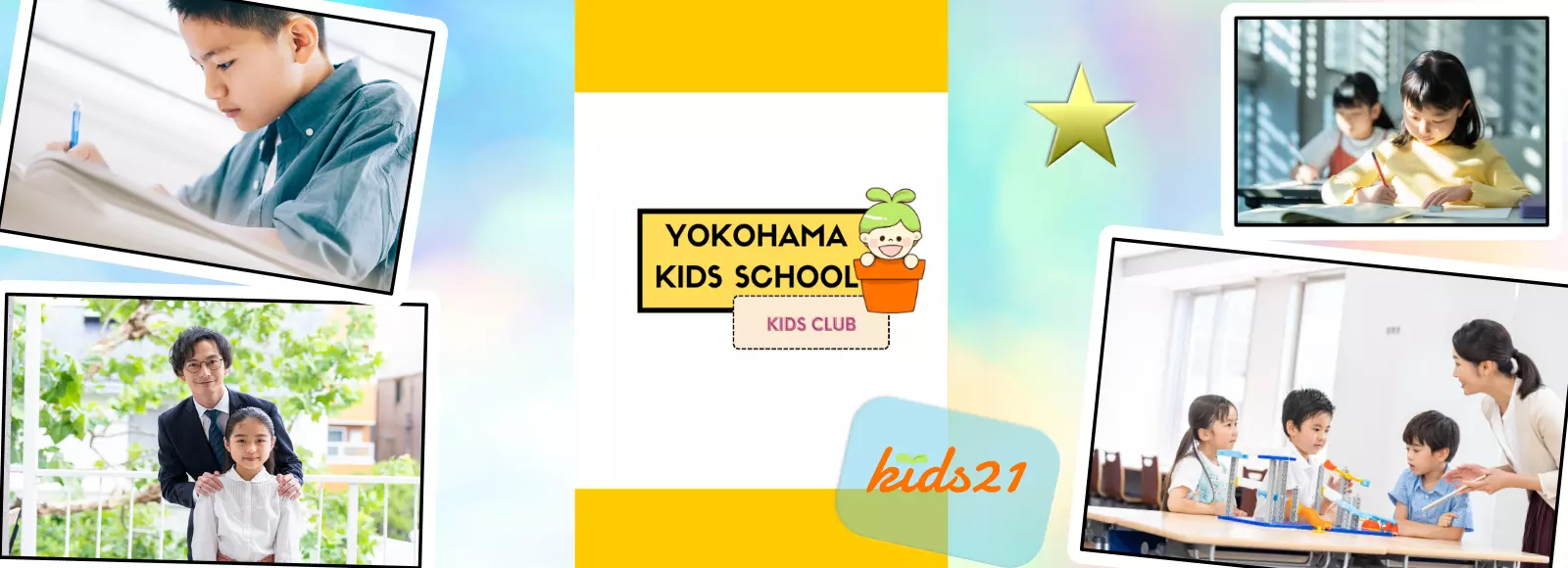アイデア収納棚で片づけ上手に!【低年齢向け】片づけるコツや方法を解説

得意ですよね。なぜ片づけが苦手なのか?自分で片付けができるようにするには?
今回の記事では、保育士の資格をもつ筆者が片づけのコツや実際に保育園で実践していた片づけ方法を解説します。
実践すれば自分でお片づけをすることができたり、お片づけがうまくなります。ぜひ参考にしてみてください。

Contents
なぜ片づけができないのか
片づけと聞いたとたん、泣いたりぐずったり…そんな経験は数えきれないほど。なぜ片づけがいやなのか、まずは原因を理解することが大切です。以下の3点が考えられます。
| 片づける場所がわからない何度も「片づけて」といわれ嫌気がさしている片づけがしづらい環境 |
片づける場所がわからない
片づけてね、といわれてもどこに片づけたらいいのかがわかりません。
とくに整理整頓が得意で細かくきっちり片づけている親御さんの場合、子ども用品についても同様に教えてしまいがちです。
大人の脳と子どもの脳はちがいます。低年齢の子どもは発達途中で「細かくきちんと」がまだ難しいのです。片づけにはコツが必要です。
キーワードは「わかりやすく」「おおざっぱに」。のちに解説しますが、ものの住所を決めると効果的です。
何度も「片づけて」といわれ嫌気がさしている
一日に何度も「片づけて」と言ってしまいがちです。だって部屋はキレイな方が気持ちがいいですから。
しかし、一日の中で子どもに何回も片づけを強制すると遊ぶ=片づけさせられるというネガティブなイメージがついてしまいます。つまり、思いっきり遊ぶことができず、遊びで刺激を受けることなく、成長していきます。
遊ぶときは思いっきり遊び、片づけの回数を極力減らすことも大切です。
片づけがしづらい環境
今使っている収納家具は子どもにとって使いやすいですか?片づけをしづらくしている要因は環境かもしれません。
収納場所が足りないからと家にある箱などで対応をすると、中身は見えず収納場所は多すぎます。小さいお子さんにはどこに何をいれるかがわかりません。
その結果、お子さんは文房具もおもちゃも空いている場所にごちゃごちゃに詰め込みます。
収納家具を見直すだけで子どもの頭の中はすっきりして、かんたんに自分ですすんで片づけができるようになります。
未就学児や小学校低学年が片づけ上手になるコツは?

小さい子でも片づけがうまくなるコツは、以下の3点です。とくに収納環境をガラリと変えてみると子どもは楽しんでお片づけをしてくれるので効果的です。
| おもちゃや勉強道具の住所を決めよう片づけの回数を1日1回にするおもちゃ収納ボックスを変えてみよう |
おもちゃや勉強道具の住所を決めよう
解決策は「ざっくり分け、住所を決める」ことです。
分け方の例としては以下のような分け方があります。
・おもちゃを「種類別」や「毎日出すおもちゃとそうでないおもちゃ」に分ける
・よく着る服、そうでない服に分ける
・「まいにちセット」をつくる。毎日宿題でつかう文房具(筆箱や下敷き)をいれておく
細かく言われてもわからないが、大まかにわけると子どもは理解できます。おもちゃ、学用品、洋服なども同様です。片づけの際、大きめのボックスやかごを使うと効果的です。
低年齢・低学年の子どもにとって1つ1つの細かい片づけは大変です。わかりやすくかんたんに物を戻す仕組みがあれば、子どもの片づけのハードルは下がります。
片づけの回数を1日1回にする
片づけは1日1回で十分です。特に小さなお子さんは遊びで発達していくため、遊びの時間を多くとることが大切です。
わが家では、お風呂に入る前に片づけタイムをもうけています。お風呂から出たときに部屋がきれいだと体も心もすっきりして気持ちがいいからです。
日中は散らかっていても目をつぶり、どうしても片づけたくなったらのちに述べる「ごほうび項目」をつくり片づけをしてもらいましょう。
回数を減らすことで、片づけに対する面倒なイメージが減ります。「遊ぶときは思い切り遊ぶ」と「片づけもしっかりやる」というようにメリハリをもつことができますよ。
おもちゃ収納ボックスを変えてみよう
幼児〜小学校低学年の子どもが日常的に使うおもちゃ、学用品、洋服のなかで特におもちゃは散らかりやすいため収納に工夫が必要です。
おすすめは「収納家具の見直し」。
100均のかごなどをつかっていた場合、安いからといって買い足してしまいがちです。収納場所が多すぎると、子どもにとって片づけのハードルが上がります。
未就学児であれば「おもちゃ収納」に特化した家具、小学校低学年児であれば「学用品収納」をメインに自分で考えて収納できる家具が適しています。
片づけ環境を一新することは心理的にもいい影響を与えます。
「このスペースにこのおもちゃを片づけたい」「自分で進んで片づけをしたくなる」など、主体的に片づけに取り組んでくれますよ。
おすすめの収納家具の紹介

収納環境を改善するにはどのような家具が向いているでしょうか。ここでは機能性が高くおすすめな家具や収納アイデアを一部ご紹介します。「価格・デザイン・機能性」で選んでいますので参考にしてみてください。
| 価格で選ぶデザインで選ぶ機能性で選ぶ |
価格で選ぶ
いざ買い替えるとなっても、急に高い家具は買えません。ここでは
リーズナブルながら使いやすさも抜群
の家具をご紹介します。
ニトリ「カラーボックス」
https://www.nitori-net.jp/ec/product/8842173s
カラーボックスと言えばニトリ。たて向きに置けばおもちゃの「見せる収納」ができ、横向きに置けば絵本棚に早変わり。中にボックスを入れれば見た目をすっきりさせることもできます。
https://roomclip.jp/photo/koo7
自由自在なアイデアで収納できるだけではなく、部屋の間取りに合わせて置き方を変えることができるのもうれしいポイントです。
現在は連結できるカラーボックスが販売されています。収納量が多ければいくつかのカラーボックスを連結させると統一感がでておすすめです。
IKEA(イケア)「トロファスト」
IKEAの大人気商品「トロファスト」
は、引き出しが複数個あり単純明快な収納ができるアイテムです。
頑丈な木のフレームで取り出しやすいプラスチック製の引き出し。フレームの木目調のデザインは部屋のインテリアとなじみやすく、フレーム部分のサイズ・形をさまざまなタイプから選択できるのも人気の理由です。
https://www.ikea.com/jp/ja/p/trofast-frame-light-white-stained-pine-50368835
引き出し部分の収納ボックスの色が選べるので、お子さんと一緒に決めると楽しいですね。
わが家でも使っていますが、幼児の力でもかんたんに引き出せるため、色別に分けた引き出しで楽しくお片づけができています。
デザインで選ぶ
収納力も大事ですが、やはり家具はデザイン性も大切です。リビングにおくならなおさらですよね。他方で、遊び心が加わった、子どもがよろこぶデザインもおすすめです。
おしゃれでリビングになじむ「安心天然木 おもちゃ収納ラック」
https://item.rakuten.co.jp/ajinashop/wf280232
リビングにもなじむ色合いのおしゃれなおもちゃ収納ラック。木のフレームは天然木素材、丸角設計で安全面にも配慮されています。
収納ボックスは、おもちゃが「見える化」された角度でどこに片づけるかがひと目でわかります。子どもが自分で決めた場所に片づける。片づけ習慣が楽しいものになりますよ。
保育園・幼稚園のグッズ収納にもおすすめ。中身がひと目でわかるため、毎日つかうものを入れておけば自分で用意ができるようになります。斜めの収納ボックスは洗濯した衣類などが入れやすく、大人にとってもうれしいポイントです。
おもちゃを楽しくお片づけ「収納ボックス 車型」
https://item.rakuten.co.jp/daimilai/lty3-al204/?scid=af_pc_etc&sc2id=af_117_0_10002089
大人から見てもワクワクする、大容量収納ボックスです。大容量では地震の際倒れてきたら…と心配になりますが、転倒防止策も施されており安心です。
子どもがよろこぶデザインが目を引きますが、とにかく収納力が抜群です。
https://item.rakuten.co.jp/daimilai/lty3-al204/?scid=af_pc_etc&sc2id=af_117_0_10002089
片づかないおもちゃも小物も、これ一台ですっきり収納できます。収納物の写真を引き出しに貼るなどすれば、子どももわかりやすいですね。
ただ難点は、子どもの目線よりも高い点です。そのため上部の引き出しには子どもがあまり遊ばないおもちゃなどをいれるのがおすすめです。
機能性で選ぶ
価格よりもデザインよりも、成長に合わせて長く使える物が良い場合は以下のような商品がおすすめです。
学用品、文房具、ランドセル、洋服まで収納「キッズハンガーシェルフ」
https://item.rakuten.co.jp/gekiyasu-kagu/1383641
おもちゃ、学用品、洋服、ランドセルなどマルチに収納できるラックです。保育園・幼稚園のグッズ収納だけでなく就学後も使い続けることができます。
おすすめポイントは2つに大別されます。
1つ目のポイントは中段の棚板。子どもの身長の変化に合わせ5段階の高さ調節が可能です。
2つ目のポイントは「自発的に整理整頓ができる」設計です。身の回りの物を全てこの1台に収納できるため、子どもの「自分でやってみたい」という気持ちを叶えてくれますよ。
リビング学習に最適「ランドセルラック&テーブル&ベンチセット」
赤ちゃん用おもつラック〜大人の作業スペースまで、長い期間使える多機能ラックです。遊び、勉強、収納がこれ1台で解決。
https://www.low-ya.com/goods/F599_G1070
機能性が高く、テーブルとベンチは使用後にラックの下部に収納できます。設置スペースが限られている場合などに適しており、とても画期的なアイデアです。
https://www.low-ya.com/goods/F599_G1070
鍵盤ハーモニカや横長のお絵描き帳なども上部ワイドスペースにすっぽり。実はベンチ部分も収納になっており、小物からかさばる物まで迷うことなくかんたんに収納できます。
機能性が高く長く使える点がポイントです。
子どもが自ら片づけできるアイデア3選

大人が言わずとも子ども自ら片づけができれば理想です。しかし急にできるわけはなく、少しづつ回数を重ねることがポイントです。日々の生活の中で実践しやすい「お片づけアイデア」をご紹介します。
| 遊び感覚で片づけを楽しむとにかく褒める(子どもにとって嬉しい声かけをする)目標時間とごほうび項目を決める |
遊び感覚で片づけを楽しむ
子どもは遊ぶことがだいすきです。片づけ=嫌なこと、という概念ができる前に楽しく片づけをする経験をしましょう。
たとえば「1曲終わるまでゲーム」。子どもが好きな曲をかけ、その1曲が終わるまでに片づけます。子どもの曲は1〜2分と短いものが多く集中力がアップ。片づけられたら必ずほめてあげましょう。
年齢が低く、1曲以内に片づけができなくても心配ありません。目的は片づけを達成する喜びを味わうことです。youtubeなどで連続再生し、出来た際はほめてあげましょう。
わが家ではいつもこの方法でお片づけをしています。はかどるようで、男の子は”鬼滅の刃”、女の子は”アナと雪の女王”、”ピタゴラスイッチ”の曲もよくリクエストされますよ。
さて、話を戻しますが「玉入れ形式」のお片づけも楽しみながらできる方法です。
幼児向けの大きめのブロックなどは、ちらかると拾い集めるのが大変です。そこで、ブロックのケースを玉入れのかごとみなし、親子で玉入れ競争ならぬブロック入れ競争をします。
外れたブロックも子どもはよろこんで取りに行ってくれますよ。
お片づけを「ゲーム」のように捉え「できたらほめる」を繰り返しやることで、成長に従いお片づけが自らできるようになります。
とにかく褒める(子どもにとって嬉しい声かけをする)
夏休みがもうすぐ明けますが怒ってばかりいませんでしたか?人は誰でも、ほめられることがうれしい生き物です。
特に低年齢の子どもはほめられることで能力が伸びます。少しでもお片づけをしていたらすかさずほめる、片づけができたらオーバーリアクションでとにかくほめてあげましょう。
片づけの最中には、その子がよろこぶキーワードで声かけをしてあげることも効果的です。
『お片づけできてかっこいいおにいさんだね』
『片づけてくれておうちがキレイになってきた』
『〇〇ちゃんのおかげですごく助かったよ』
子どもはよろこび、もっと頑張ろうという気持ちになります。
わが家では「具体的にほめる」ことを繰り返した結果、自らお片づけができるようになりました。
『〇分で片づけができてすごいね』
『このおもちゃはこの場所だってよくわかったね』
具体的にほめることで子どもは、お片づけをちゃんと見てくれていることをうれしく感じます。
そうはいっても毎回ほめることは難しいですね。大切なことは、お片づけすることを当たり前に考えないことです。「気づいたらほめる」を継続して実践するだけで肯定感が育まれ、自らお片づけができるようになります。
目標時間とごほうび項目を決める
「〇分までに終わらせよう」「お片づけができたらおやつにしよう」というように、目標時間やごほうび項目を決めると、子どもはお片づけがはかどります。
しかし時計が読めない子も多いはず。「長い針が一番上までいくまでがんばろうね」などかんたんな声かけをしましょう。
また、目標時間は好きなテレビが始まるまで、お風呂の時間まで、寝る前の時間など、機嫌よくスムーズにしてくれそうな時間帯を見計らって声を掛けてみましょう。
ごほうび項目を決めるとお片づけに絶大な効果がありますよ。
・お片づけができたらおやつタイム
・進んでできた日は特別なおやつにする
・終わったらお母さんとこの遊びをする
・終わったら公園に行く
など、お子さんの好きなことをごほうび項目に設定してみましょう。
わが家では、幼児にはおやつ、小学生にはお小遣い項目を設定しています。お片づけをするとごほうびが得られるので、頑張ってお片づけができています。
「楽しみ」と「片づけ」をセットにしてあげると、親子で楽しみながらも自らお片づけができるようになりますよ。
大切なのは片づけしやすい環境づくり

幼児や小学校低学年ではまだまだ、片づけできないお子さんばかりです。そんなお子さんのために大人のフォローや環境づくりが必要です。
つまり、大人が日頃から片づけをおこない部屋をキレイにする姿勢を見せたり、お片づけをフォローすることで「子どものお片づけ力」は上達します。
そのほか、学用品やおもちゃなどの収納家具を一新するのも効果的な方法です。この機会にぜひ収納を見直して、お子さんと片づけを楽しんでくださいね。
参考URL:
https://kinarino.jp/cat3/25672
https://39mag.benesse.ne.jp/living/content/?id=36378
https://kurashi.biglobe.ne.jp/rankings/10049
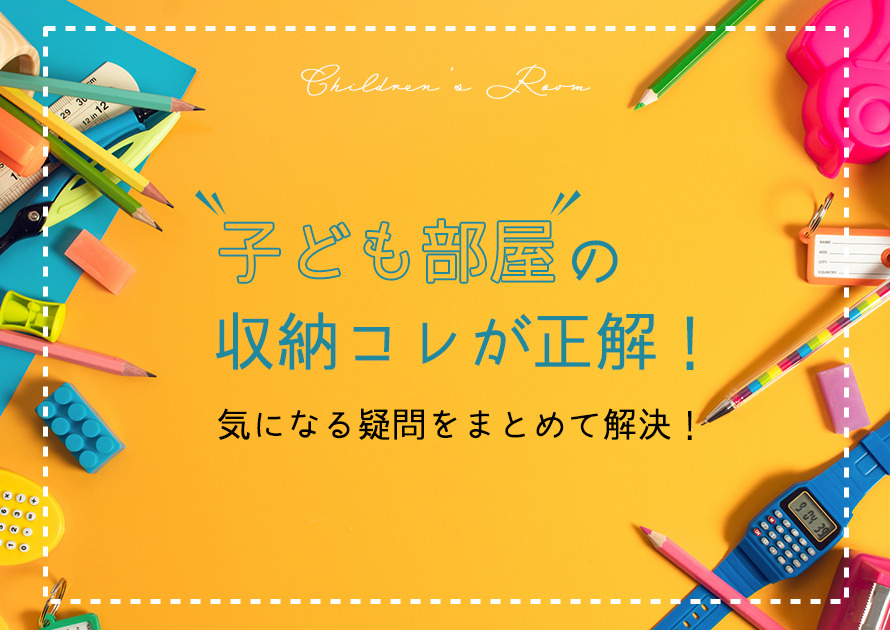

https://keep-it.jp/mag/storage-info/265